あの娘の事は
時間はいつだって怒涛のように流れ去っていくせいで僕一人がおいていかれてばかりなのはいつものことだけれど、寂しいと言うには僕は長生きしすぎていて今更何の文句も言えないものだから、時々僕は北ノ庄がもうここにいないことにびっくりしたりするのだけれど、またその忘れ形見が美人になったものだからそれにも驚いたりするのだ。
「……福井も美人さんになったよねえ」
「さばばー何言ってるのさ、うちの本家が美人なのは今に始まったことじゃないでしょ」
「まあねえ」
小浜や美浜が何言ってんだこいつらと言う顔をしてるけど、彼らは彼らの価値観があるので強制するつもりはないがどう客観的に見ても福井は美人と呼ぶべきだろうと僕らは確信している。
「敦賀、あの二人っていつもあんな感じなん?」
「まああんな感じと言うか割と常に『うちのお姫さんは常に最高にかっこいい』的な感情はたまに見えますね」
「はー……越前はほんといまだにわからんわ」
敦賀も小浜も随分な言いようである。
北の庄譲りの初雪のように白い肌と鋭利な刃物に似た目、そして武道によって鍛えられたすらりとした体つき、あれを美人と称せずに誰を美人と称するのであろう。
まあつまり一言で要約すると、『うちの県庁所在地様は今日も最高』という話である。
ただただ福井が好きすぎる鯖江の話。
「……福井も美人さんになったよねえ」
「さばばー何言ってるのさ、うちの本家が美人なのは今に始まったことじゃないでしょ」
「まあねえ」
小浜や美浜が何言ってんだこいつらと言う顔をしてるけど、彼らは彼らの価値観があるので強制するつもりはないがどう客観的に見ても福井は美人と呼ぶべきだろうと僕らは確信している。
「敦賀、あの二人っていつもあんな感じなん?」
「まああんな感じと言うか割と常に『うちのお姫さんは常に最高にかっこいい』的な感情はたまに見えますね」
「はー……越前はほんといまだにわからんわ」
敦賀も小浜も随分な言いようである。
北の庄譲りの初雪のように白い肌と鋭利な刃物に似た目、そして武道によって鍛えられたすらりとした体つき、あれを美人と称せずに誰を美人と称するのであろう。
まあつまり一言で要約すると、『うちの県庁所在地様は今日も最高』という話である。
ただただ福井が好きすぎる鯖江の話。
PR
140文字SS画像まとめ
自分用にお遊びで作ってみたものまとめ。
たぶんそのうち増える。下に行くほど新しくなります。
お借りしました
*過去ログ
2018年秋以降のログ
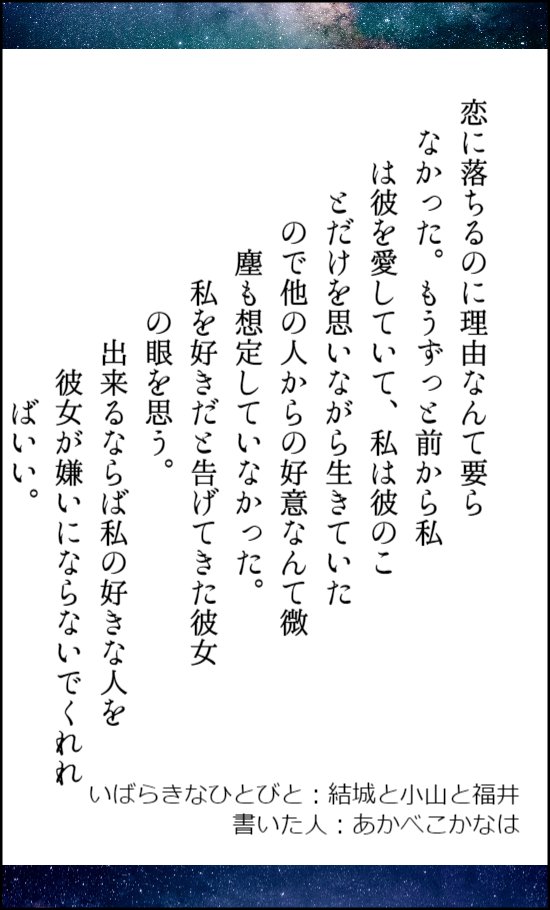
結城福井小山。

カラフルロケット姉弟
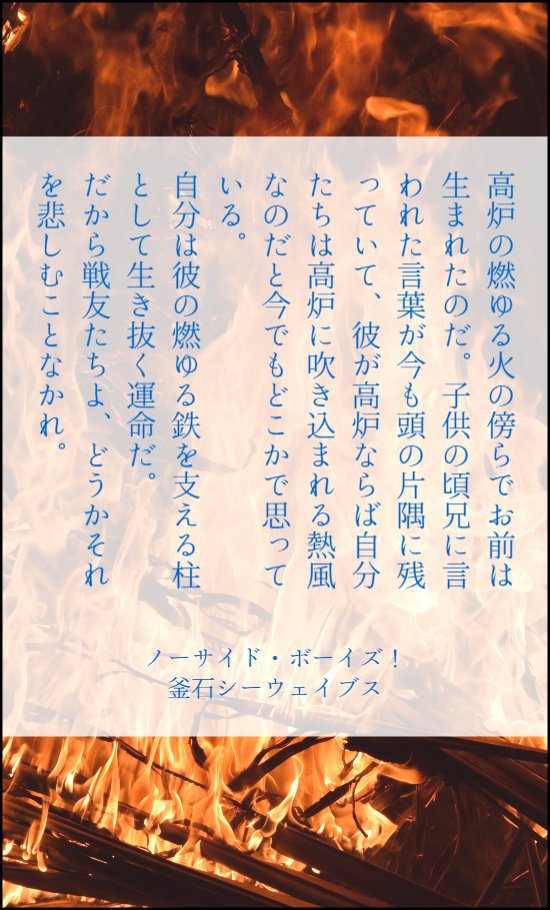
シーウェイブス
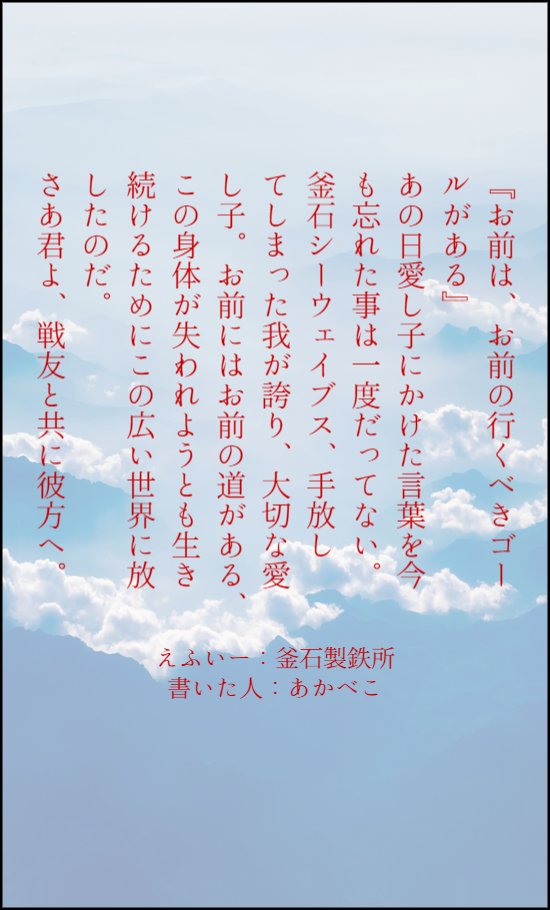
↑の釜石視点

下館

スティーラーズとシーウェイブス。

結城福井

結城小山

「走る男と追う女」のニセ同人誌サンプル


「君に還る日のために」のニセ同人誌サンプル

ファインティングブルとスティーラーズ

此花と職員さん

八幡釜石

ジュビロとシーウェイブス

シャイニングアークスとレッドハリケーンズ

スティーラーズとシーウェイブス

戸畑と八幡(L版なので少し大きめです)

八幡釜石

鹿島と此花
たぶんそのうち増える。下に行くほど新しくなります。
お借りしました
*過去ログ
2018年秋以降のログ
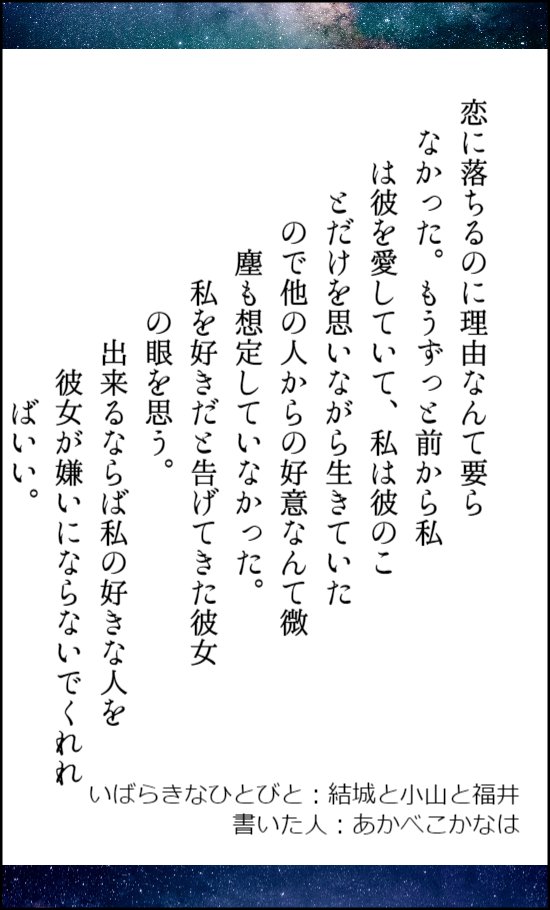
結城福井小山。

カラフルロケット姉弟
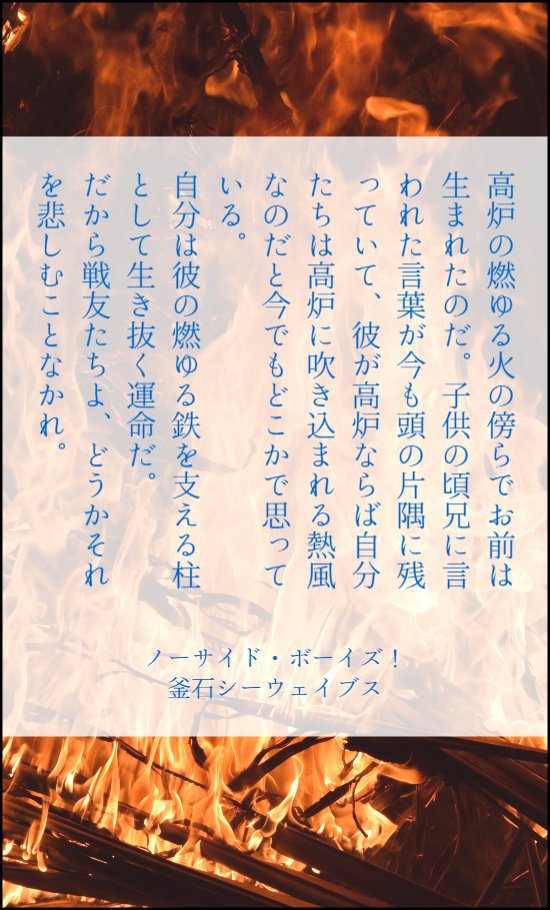
シーウェイブス
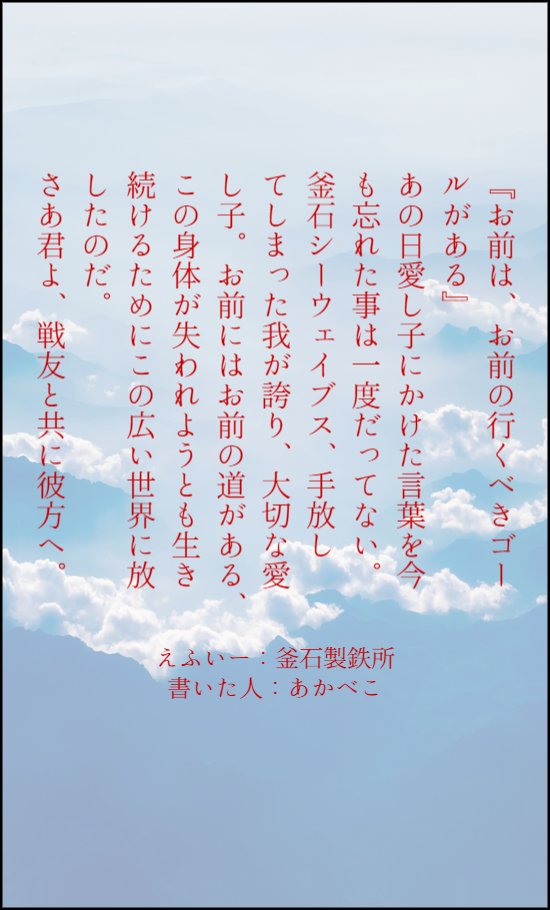
↑の釜石視点

下館

スティーラーズとシーウェイブス。

結城福井

結城小山

「走る男と追う女」のニセ同人誌サンプル


「君に還る日のために」のニセ同人誌サンプル

ファインティングブルとスティーラーズ

此花と職員さん

八幡釜石

ジュビロとシーウェイブス

シャイニングアークスとレッドハリケーンズ

スティーラーズとシーウェイブス

戸畑と八幡(L版なので少し大きめです)

八幡釜石

鹿島と此花
広島ダービーの憂鬱
はっきり言って調子は良くない。
強いチームとの試合が続いてまともに勝ち点をあげられず、出来ることは最善を尽くすことばかり。
「久し振りじゃのう、坂」
「……今はレッドレグリオンズですよ、マーズあにさん」
血縁関係はないけれど尊敬の念を込めてそう呼ぶようになってもうずいぶんになる。
ようやく今シーズン一勝をあげたばかりのあにさんと違い、俺の方はさっぱり勝てないのが現実だ。
「にしてもホント急に髪がふわっふわになりよって、前はもっと直毛じゃったろうに」
「チームの名称の変化なんかで容姿が多少変わるのはよくあることでしょう?」
「まあなぁ」
そうして天然パーマになった髪を軽くなぜた。
チームの変化が容姿に直接影響するとは分かっていても急に髪質が変わるというのは予想してなかったので、このふわふわの髪には正直まだ慣れていないのが本音だ。
「……憂鬱そうじゃな」
「そりゃあ憂鬱ですよ」
「なら、勝てばええ」
「はい?」
「簡単じゃろう?」
「勝てないから憂鬱なんですけどね」
「ホントになあ」
彼は親譲りの美しいかんばせを歪めて自嘲気味に笑う。
「努力をすれば愛して貰えるが、勝てなければ降格するしかない。勝てる相手には確実に勝つしかわしらに道はないんじゃ」
ラグビーは戦力と戦術がすべてだ、番狂わせなんてめったに起きるもんじゃない。(だから日本代表が南アフリカに勝ったことが奇跡だったのだ)
それでも僕らはこの競技に恋をし、その道を追うことを選んだ。
「悪いが、勝ち点は貰っていくぞ」
「……嫌ですよ」
残りたい。
たとえどれだけ負け続けていても、ここにいれば成長できると言う事は肌で感じていた。
「なら、せいぜい苦戦させとくれ」
ブルーズマーズとレッドレグリオンズ。
ちょうど今日広島ダービーだったので(結果は確認済み)
強いチームとの試合が続いてまともに勝ち点をあげられず、出来ることは最善を尽くすことばかり。
「久し振りじゃのう、坂」
「……今はレッドレグリオンズですよ、マーズあにさん」
血縁関係はないけれど尊敬の念を込めてそう呼ぶようになってもうずいぶんになる。
ようやく今シーズン一勝をあげたばかりのあにさんと違い、俺の方はさっぱり勝てないのが現実だ。
「にしてもホント急に髪がふわっふわになりよって、前はもっと直毛じゃったろうに」
「チームの名称の変化なんかで容姿が多少変わるのはよくあることでしょう?」
「まあなぁ」
そうして天然パーマになった髪を軽くなぜた。
チームの変化が容姿に直接影響するとは分かっていても急に髪質が変わるというのは予想してなかったので、このふわふわの髪には正直まだ慣れていないのが本音だ。
「……憂鬱そうじゃな」
「そりゃあ憂鬱ですよ」
「なら、勝てばええ」
「はい?」
「簡単じゃろう?」
「勝てないから憂鬱なんですけどね」
「ホントになあ」
彼は親譲りの美しいかんばせを歪めて自嘲気味に笑う。
「努力をすれば愛して貰えるが、勝てなければ降格するしかない。勝てる相手には確実に勝つしかわしらに道はないんじゃ」
ラグビーは戦力と戦術がすべてだ、番狂わせなんてめったに起きるもんじゃない。(だから日本代表が南アフリカに勝ったことが奇跡だったのだ)
それでも僕らはこの競技に恋をし、その道を追うことを選んだ。
「悪いが、勝ち点は貰っていくぞ」
「……嫌ですよ」
残りたい。
たとえどれだけ負け続けていても、ここにいれば成長できると言う事は肌で感じていた。
「なら、せいぜい苦戦させとくれ」
ブルーズマーズとレッドレグリオンズ。
ちょうど今日広島ダービーだったので(結果は確認済み)
戦友よ、俺は帰ってきた!
ぴくぶらのお題企画参戦用に書いたもの。
BLと言うかブロマンス寄りのif話です。
BLと言うかブロマンス寄りのif話です。
カテゴリー
カウンター
忍者アナライズ

